
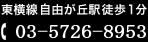

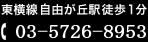


こんにちは。スタッフの清水です。
ひさしぶりの更新になります。
7月に入ってから暑い毎日が続いておりますが、体調など崩されてはいませんでしょうか?
みなさま、熱中症にはくれぐれもご注意くださいね!
さて今日は、お口の中で大切な役割をしているものについてお話します。
「お口の中で大切な役割をしているもの」といわれたら、なにを思いつきますか?
舌? 正解です。舌がなければ味覚がありません。
歯? 正解です。歯がなければ咀嚼ができません。
歯ぐき? 正解です。歯ぐきがなければ歯を維持することができません。
どれもとても大切な役割を担っています。
そしてもう1つ。意外と普段は気にしないことが多いかもしれませんが、
「唾液」もとても大切な役割を担っているのです。
唾液はお口の中で、こんなはたらきをしています。
①抗菌作用・・様々な抗菌物質により、細菌の発育を抑制する。
②希釈、洗浄作用・・細菌や食べかすなどを希釈し洗い流す。
③歯の保護・・唾液中のたんぱく質により、ぺリクルを作り歯を保護する。
④歯の再石灰化・・脱灰して失われたカルシウムやリンを補う。
⑤免疫作用・・唾液中の成分が、口腔内細菌に様々な防御反応を起こす。
⑥緩衝作用・・酸性に偏った環境を中性に戻す。
こうした唾液のはたらきは、私たちを虫歯や歯周病から守ってくれています。
つまりお口が乾くと、こんなことが起こってしまいます。
①虫歯や歯周病の発症・増悪
②たべものが飲み込みにくい
③舌や唇、口腔内がヒリヒリする
④味覚が鈍る
『お口の乾燥感を持つ方は、ご年齢が高くなるにつれて増えている』
というデータがでています。65歳以上の方の約56%が自覚されているそうです。
そこで、ご自身でもできる唾液の分泌を促す方法をご紹介します。
〈方法1:よく噛む〉
お食事はよく噛んで食べるようにしましょう。
モグモグしっかり噛んでお口を動かすことで、唾液の分泌を促進します。
シュガーレスガムなどを噛むのもいいですね。
〈方法2:湿潤剤〉
お口の保湿剤を使うのも1つの方法です。
湿潤剤を指先や歯ブラシにとり、お口全体にいきわたらせたら
しばらくしてからペッと吐き出す、というのが一般的な使用方法です。
モノによって成分や質が異なるので、湿潤剤を初めてお使いになる方は
ご自身に最もあうものをお使いいただくことをおすすめします。
〈方法3:マッサージ〉
頬や唾液腺をマッサージすることで、唾液の分泌を促進します。
手のひらを頬におき、指先を耳下腺、親指の付け根を顎下腺にあて、
それぞれを刺激するように円を描いてマッサージをします。
次に、両手の親指を舌下線にあて、軽く刺激します。
これらをゆっくり10秒ずつおこないます。
※このとき、唾液が分泌されている感覚を感じることがポイントです。
3つの方法をご紹介しましたが、1と3はいつでも簡単にできそうですね!
お口の乾燥感でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

先日のブログに書いていただいておりますが・・
7月の上旬に誕生日をむかえ、先生方にお祝いしていただきました。
ありがとうございましたm(_ _)m
まだまだ未熟者な私ですが、これからもっともっと知識も技術もレベルアップできるよう
そして、患者様から愛されるスタッフになれるようがんばります!!
清水美咲
「前歯にキレイなインプラントを入れたい」、「古い被せ物からきれいな歯に取り換えたい」、「歯並びがずれているので治したい」等々・・・
患者様は高い審美性を求められるものです。
「だけど治療したらどんな感じになるんだろう・・?」
最終ゴールが予想できない状態で治療を進めていくことは大変危険なことです。
このような切実なご要望にお応えするために、必要な診察や検査を行ったり、術前にできる限りの情報収集をするのは当然ですが、患者様の希望される補綴治療がどのようなものであるのかを「具体的にみきわめること」が大切となります。
インプラント補綴や審美修復治療にあたっては治療計画を立てる前に、上下顎の模型を咬合器に装着し、
・歯列の状態
・欠損部顎堤の状態
・咬合関係
・咬耗
・咬合誘導様式
・歯の挺出の有無
・欠損部顎堤と対合歯とのクリアランス
などを確認し、事前に分析しておくことは治療により得られる患者様の利益や恩恵と、それに対するリスクを考慮し検討するうえで大変重要となります。
とくにインプラント治療においては欠損部位のみならず、残存歯も含めた補綴治療に対する総合的な患者様のご希望を十分に考慮したうえで、治療の最終目標となる上部構造物を想定して、模型上に診断用ワックスアップ
を行います。
この作業は顎骨のレントゲンやCT画像検査とともにインプラント体の埋入方向やサイズを決定するための生体力学的検討を行ううえでも非常に重要となります。

「上顎インプラントの前の診断用ワックスアップ」
多数歯欠損では、噛み合わせを記録して模型を咬合器に装着します。
そののちに、最終的な上部構造を想定したワックスアップを行います。
万が一重度な骨喪失により歯が大きくなると予想されたり、隣在歯とのバランスが悪い場合は軟組織や硬組織の造成処置などを検討します。

「歯並びを被せ物で回復する前の診断用ワックスアップ」

「1歯欠損のケースでも慎重にバランスを確認するためには行います」
当院のインプラント、審美修復ではルーティンワークです。
事前の細かな審査により多くのエラーを回避でき、より審美的で調和のとれた治療が可能となるのです。
院長 髙木謙一
去る7月20~21日の2日間にかけて私が日本支部の実行委員を務めているICOI(国際口腔インプラント専門医学会)の「2013 ICOI Japan Symposium」が東京国際フォーラムで開催されました。今年も参加者は500名を超えたそうです。来年は日本が世界規模で行われる最も大きなWorld Congressの開催地となりますので年明けから月1回のペースで実行役員の会議も行われてきました。

今回このICOIのインパクトファクターが上昇し、1.404になり、世界で選ばれた82学会中の36位となったそうです。
インパクトファクターとは自然科学、社会科学分野の学術雑誌を対象として、その雑誌の影響度を測る指標のことです。
ユージン・ガーフィールドが1955年に考案したもので現在は毎年トムソン・ロイターの引用データベースWeb of Scienceに収録されるデータを元に算出されます。対象となる雑誌は自然科学5900誌、社会科学1700誌です。その値はJournal Citation Reportsのデータのひとつとして収録されます。

ICOIの学会誌 「Implant Dentistry」
診療の傍ら、休日は学会活動などもあり、ゆっくりと休む時間もない日々が続いておりましたため、少々疲労気味でした。
この日は朝から参院選の投票にいき、そのまま学会場に向かいました。
日曜日の学会は早い時間に閉会となったこともあり、その後は息抜きのため「銀ブラ」しました。日も長くなり、この日は暑さも和らいで気持ちが良かったです。
国際フォーラムの横を通り抜けて銀座へ向かう途中「パティスリー・サダハル・アオキ」を発見。

こちらは丸の内店。マカロンやカラフルなケーキで有名ですが、私はこちらの「シュークリーム」が大好きなので立ち寄りました。
まだ食されていない方にはオススメです。ただし、クリームの量が尋常ではないです。

一見普通の大きさに見えますが、中は底までクリームがびっしり詰まっています。(注)スウィーツ男子ではありません。


ブラブラ歩いて銀座で中華を食べて・・・

最後にビール専門バーで喉を潤していい気分。良い解消になりました。
この発散パターンよくないですね(笑)
このところ当院にはインプラントや歯並びのご相談、審美回復を希望される方等々・・多くの方々が来院されております。
今週も上顎多数本のインプラント手術を控えておりますのでこの暑さに負けず「患者様お一人お一人に見合った審美的で長期に安定するやり直しのない質の高い治療をモットーに」気を引き締めて診療に臨みたいと思います!
院長 髙木謙一
こんにちは。院長の髙木です。
本日7/6関東では梅雨明けしたとみられると発表されました。
平年よりとても早い梅雨明けですね。
それにしても今日はとても暑かったですね。熱中症に注意です!
さて今日はいつも元気で明るいスタッフ清水さんの誕生日でした。

いまや世界のパティシエ辻口博啓氏の第1号店「モンサンクレール」のケーキをお昼に皆で食べてちょこっとお祝いをしました。
清水さんは毎日とっても頑張ってくれていますね!この場を借りて改めて感謝します!!とても責任感が強く、仕事も早いので患者様も安心してご通院していただけています。
もうすぐ1年ですがこれから更にステップアップして下さい!
「happy birthday!」今晩はしゃぎすぎないようにして下さいね。
院長 髙木謙一
インプラントの二次手術とは、2回法インプラントシステムにおいて、一次手術で顎骨内に埋入されたインプラント体
の上部にアバットメントとよばれる装置を連結する外科処置のことをいいます。
その目的は補綴治療を開始するためにインプラント体の粘膜貫通部を形成することです。
一般的には一次手術後に下顎で3か月、上顎で6ヶ月以上経過したのちに行われますが、当院ではオッセオスピード
インプラントを使用することで期間を短縮することができます。
二次手術では、貫通部の形成の他にも貫通部周囲の軟組織に対するマネージメントを考慮する必要があります。
具体的には、非可動性粘膜の保護や獲得により、上部構造周囲の軟組織形態の維持や改善をはかることが可能で
あり、最終的な上部構造にも大きな影響を与えます。そのため、インプラント治療においては重要な処置の一つといえます。
本日右下6部に2回法でインプラント手術をした方の二次手術がありましたので今回は臼歯部における二次手術に
ついてご説明します。

臼歯部においては、口腔前庭が浅いために角化粘膜の幅が狭いことが多いのが特徴であります。
臼歯部では前歯部よりも精密な審美性は要求されないものの、軟組織の安定性や機能性が重要となります。
二次手術では創面の閉鎖を達成し、厚く幅のある角化付着粘膜を形成します。そのため、臼歯部での二次手術において
は角化付着粘膜と遊離粘膜の境界を考慮して手術を行います。
理想的にはインプラント周囲に幅4mm程度の角化付着粘膜が存在すれば、口腔内環境に十分耐えうる機能の獲得が可能
となります。その機能性を得るには、インプラント体周囲組織にも天然歯に類似した生物学的幅径を形成させることがインプラント
の保護にもつながり重要となります。そのため、軟組織の切除などによる侵襲は最小限にとどめ、万一、十分な角化付着粘膜
が獲得できず軟組織の安定性を欠く場合には、遊離粘膜移植および結合組織移植などを行います。
二次手術の際に、インプラント体上部は軟組織により被覆されているため、埋入位置の確認ができない場合が多いのですが、
その場合には一次手術で使用したサージカルガイドプレートを再度使用してインプラント体の位置を決定することにより、軟組織の
損傷を最小限にすることができます。インプラント周囲組織に問題がない場合には、基本的に切開をインプラント埋入部位直上に
行いその位置を確認します。複数本埋入した場合や軟組織の厚みが足りない場合には、切開を口蓋側に行い粘膜骨膜弁を唇側
に移動することにより、角化付着粘膜の厚みを獲得することができます。また、歯間乳頭を形成するために、隣在歯の歯肉を温存
した切開法やパンチブレード(歯肉粘膜穿孔器;カバースクリュー上の軟組織のみを切除する円筒状の刃物)を用いることもあります。


パンチブレード<BIOPSY PUNCH (株)カイ インダストリーズ>
カバースクリューが確認できない場合には、埋入部位に一直線に切開を加えます。また、角化粘膜の厚みが十分に存在する場合
には侵襲を抑えるためパンチブレードを使用して、カバースクリューの粘膜骨膜を切除します。前者の方法は、後者と比較して侵襲が
大きくなる欠点があります。後者の方法は比較的侵襲が少なく施行可能であり術後の粘膜が早く治癒します(ただし、幅が十分に
ない場合に用いると角化歯肉を減らしてしまうので注意が必要です)。
以下は当院での選択基準となります。
<二次手術法の選択基準>
歯槽堤の角化歯肉幅 二次手術法
8mm以上 パンチアウト法
4mm以上 歯槽頂切開法
1mm以上 歯肉弁根尖側移動術
0mm以上 遊離歯肉移植
インプラント周囲角化組織の必要性については賛否両論とされておりますが、私はこれまでの経験上絶対に必要だと考えております。
その必要性として
・可動性粘膜は機械的刺激に弱い
・頬粘膜の動きがインプラント辺縁軟組織に波及する
・インプラントと周囲組織との結合が天然歯と比較して脆弱
・インプラント周囲組織の対プラーク抵抗性が天然歯と比較して弱い
などが挙げられます。
インプラント体上部が確認された後、インプラント体のプラットフォーム周囲に新生骨が覆っているような場合は除去します。
そして、必要な高さのアバットメントを選択するため、角化粘膜の厚みを計測します。
治癒後に適切な状態の角化粘膜が得られ、軟組織がヒーリングアバットメントを被覆しないように十分な高さがあり、さらに対合歯
と接触しない高さのものを選択します。
万一大きな粘膜弁を形成した場合には、インプラント周囲の粘膜が収縮しやすくなるため、縫合する場合には、アバットメント周囲に
緊密に縫合するようにしております。パンチブレードによる方法では基本的に縫合は行いません。
ヒーリングアバットメントとインプラント体の確実な適合度合いを確認するため、術後にデンタルエックス線写真を撮影します。
万一不適合が生じた場合には、インプラント体周囲に感染を生じることがあるため、除去して再度装着します。
ただしこれらアバットメントの取り外しは一度顎骨内に埋入されていたものを外界に露出させる行為ですので、その都度必ず細菌が
侵入してきます。それにより骨の防御反応として骨が吸収する訳です。
二次手術後、ヒーリングアバットメント周囲にはプラークが付着しやすため、ブラッシング、含嗽などを行い、口腔内を清潔に保ちます。

そして、軟組織が安定した形態に落ち着くまで十分期間をおき、その後に印象採得を行います。
二回法インプラントは、二次手術時に軟組織形態の修正がある程度できる利点があります。
当院では随時インプラント無料カウンセリングを行っておりますので是非お気軽にご相談下さい。
院長 髙木謙一(ICOI国際口腔インプラント専門医学会米国認定医・同日本支部役員)
こんにちは。スタッフの清水です。
先日“梅雨入り”が宣言されましたが、雨も降らずいいお天気続きですね。
日中は暖かいというよりむしろ暑いくらいで、もう夏がきてしまったような気分です♪
さて話は変わりますが・・
皆さまは、外食した際にテーブルが拭かれていなかったり、洗ってない食器に料理が盛られていたり、
また、前のお客さんが使ったお箸やスプーンを使って食事をすることなど考えられますか???
答えはもちろん 「考 え ら れ ま せ ん!」 ですよね。
歯科医院において『完全滅菌消毒』をしないということは、それよりもっと不潔で危険なことなのです。
(血液や唾液などの体液が付着することが多いからです。)
当院では、安心して治療を受けていただくために院内感染予防(滅菌消毒システム)を徹底しております。
まず、紙コップやエプロンなど滅菌できないものは、患者様ごとに使い捨てのディスポーザブルです。
毎回新しいものをご用意し、お使いいただいています。

使用された器具は、「水洗・洗浄」 → 「 薬液浸漬 」 → 「超音波洗浄」 → 「オートクレーブ(高圧蒸気)滅菌器 」を行いて、次に使用するまでの間、「紫外線保管庫に保管」されます。
先ほどから「滅菌」というコトバを使っていますが、「滅菌」は「殺菌」や「消毒」などと何が違うの?
と思った方はいらっしゃいませんでしたか?
「滅菌」 「殺菌」 「消毒」について簡単にご説明します。
滅菌:細菌やウィルスなどの微生物を有害・無害を問わず“全て”死滅させること。
殺菌:菌を殺す、という行為そのもののこと。
消毒:細菌の量を減らしたり、一定レベルの細菌を死滅させたりすること。
皆さまもご存じかと思いますが、消毒にはアルコールを使用します。
70度以上のアルコールで細菌を減らしたり、一定レベルの細菌を死滅させたります。
滅菌には一般的に『オートクレーブ』という滅菌専用の機械を使用します。
器具に付着した微生物が滅菌機のなかで130℃以上の高温な蒸気にさらされることによって
微生物を構成しているタンパク質が変化を起こし、死滅します。


器具やスタッフ自身の感染対策予防はもちろんのこと、スリッパや診察室も患者様ごとに消毒・殺菌し
常に清潔な状態を保てるようにしています。


診療終了後にはバキューム、排水パイプ、スピットンなども薬液を使用して洗浄します。
このようにして、院内の感染予防対策を徹底しております。
ご自身の目で直接見て確認できないことなので、ご不安がある方もいらっしゃるかと思います。
患者様の目に届かないことだからこそ、「より安心して治療を受けていただけるよう」に当院では今後も感染予防や衛生管理を徹底的に行ってまいります。
スタッフ 清水美咲
すっかり初夏を通り越し、夏のような気候が続いております。
梅雨前のひととき、しっかり体をあたためてリラックスしておきたいですね。
先日院内での差し入れに
スイスのチョコレートショップ、リンツのドリンクをいただきました!
定番のチョコレートドリンクも美味しいですが、
期間限定のホワイトチョコレートストロベリーアイスドリンクはパーフェクト!!です。
見ているだけで癒される可愛らしいルックス、
ナチュラルな甘さとくせのない、期待を裏切らないお味。。。。大満足!
五月中、無くなり次第終了とのことです。
さて、冷たいもの、と聞くと歯の痛みやしみる感じを連想される方、いらっしゃいませんか?
お口にして少しでもそういった不快症状を感じると美味しさも半減してしまいますよね。
いわゆる「象牙質知覚過敏症状」と言われる状態なのですが、実際どういった現象がこの症状を引き起こしているのでしょうか?
象牙質とは、歯の表面の硬いエナメル質の内側にあり、最深部の神経と直結した組織のことです。
簡潔に言いますと、なんらかの原因で本来覆われているはずの象牙質がむき出しになっている部位があり、そこに加わる刺激が直接伝わり、
全て痛みとして伝達されている状態、なのです。
しかし、象牙質を露出させる原因としてはさまざまあり、
強いブラッシング
歯をぐらつかせるような強い歯ぎしり
歯を摩耗させるような強い歯ぎしり
虫歯
炭酸飲料など酸性食品の過剰摂取 など・・・さらに複数の原因が関与する場合もあります。
むき出しになった象牙質にふたをする治療だけでは、何度でも再発を繰り返すことがあります。
一本の歯だけでなく、総合的に診断することが、症状改善の近道です。
気になるご症状がある場合、また予防とチェックをご希望の方、ご連絡、お待ちいたしております。
こんにちは。スタッフの清水です。
少し前になりますが、ゴールデンウィークということで、4日間お休みをいただきました。
どこに行っても混むと分かっていたので、のんびり過ごそうかな~と思っていましたが、
せっかくの連休!!ということで、『鎌倉・江の島の旅』に行ってまいりました。
お天気も良く、日差しもちょうどよくポカポカでお出かけ日和でした!
電車で鎌倉駅まで行き、西口方面へ。 お寺・神社をまわることにしました。
最初に訪れたのが、『寿福寺』
本堂を覗いてみましたが、ヒヤーっとした何とも言えない空気を感じました。
教科書で学んだ、あの歴史の世界がここにあったのか~。と思うと
とても不思議な気持ちになりました。 (結構、歴史に興味があるんです♪)
門を跨ぐのも、石畳を歩くのも、建物を見るのも、香りを感じるのも
1つ1つに何か感じるものがありました。
脇の砂利道を上ると、北条政子と源実朝のお墓と伝えられている五輪塔があります。
(一応、お墓なので写真は撮っていません。)
横穴式墓所(やぐら)は、鎌倉地方特有の墓所の形だそうで、
その中にひっそりとしている感じが、また雰囲気を醸し出していました。
次に、『海蔵寺』へ向かいました。
こちらでは、有名な十六の井戸を見ました。
洞の中に16個の穴が掘られていて、そこに溜まる湧水は鎌倉時代から今日まで
湧き出つづけているそうです。
海蔵寺を後にし、少し険しい道をのぼり、『源氏山公園』へ。
源頼義や源頼朝が戦の戦勝祈願をした地として有名な場所ですね。
この頼朝の堂々たるお姿・・。 素敵です♪笑
最後に銭洗弁財天宇賀福神社へ、お参りに行きました。
名所ということもあり、沢山の人で賑わっていました。
かつて、源頼朝が受けたお告げにより建てられた神社で、のちに北条時頼がこの湧水で
銭を洗い一家繁栄を祈ったことから、周りの人々も銭を洗って幸福祈願をしたそうです。
私もその湧水でお金を洗い、幸福祈願をしてまいりました。
帰り道に、佐助稲荷神社に立ち寄り、こちらもお参りをしました。
他の名所や、お参りしたい神社やお寺もたくさんありましたが、
江の島へ行く予定があったので、切り上げることにしました。
駅に戻り、初☆江ノ電 に乗り、ギュウギュウ電車で30分ほどかけて江の島へ!
鎌倉以上にたくさんの人でにぎわっていました!!
右も左も前も後ろも、とにかく人!人!人!人!!!!!!!!!
江の島ではほとんどなにもできませんでした(;o;)
昼食に行く予定だった 生しらす丼のお店は受付終了。
他のお店も入れる様子がなかったので、諦めることにしました。
ほんっとーーに悔しかったですが、道を歩くのも精一杯なくらいです。
さすがに「諦めも肝心だ。」と思いました。
今度は平日の休日にリベンジしようと思います!
やっぱり旅行は、人や時間に追われずのんびりしたいものです♪
・・と、私の旅日記になってしまいました。長々と失礼いたしましたm(_ _)m
皆様はどのようなゴールデンウィークをお過ごしになりましたでしょうか?
先週は連休明けということもあって、少しお身体が重~く感じる方も多かったのでは?
また、これから6月・7月と夏に向けて暑い日も増えていきそうですね。
疲れや気温の変化でご体調を崩されないようにお気をつけください!!
あ!そしてもう1つ・・
先週、大大大大好きな富士急ハイランドにも行ってきたんです!!!
最近は、休日に少し遠出をするのがマイブームです☆
清水 美咲
本年5月17日より金曜日の診療を開始します。
患者様により良いサービスをご提供させていただくため
今後とも一層努力をしてまいります。
宜しくお願い申し上げます。
ゴールデンウィーク期間の休診日をお知らせ致します。
4/29(月) 休診
4/30(火) 診療
5/1(水) 診療
5/2(木) 診療
5/3(金) 休診
5/4(土) 休診
5/5(日) 休診
5/6(月) 休診
5/7(火)~ 通常診療
となります。
患者様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。