
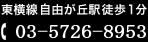

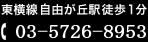


誠に勝手ながら令和7年12月29日~令和8年1月4日まで休診とさせていただきます。
令和8年1月5日より通常診療となります。
ご迷惑をおかけいたしますがご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
髙木歯科自由が丘クリニック
誠に勝手ながら令和7年8月9日~令和8年8月16日まで休診させていただきます。
8月18日(月)~通常診療となります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
髙木歯科自由が丘クリニック
院長の髙木です。この度自由が丘1丁目29番地区第一種市街地の大規模な再開発事業に伴い、自由が丘南口に移転させていただき、本年4月より診療を再開いたしましたのでお知らせさせていただきます。
移転開業に時間を要し、ご通院されている患者様には多大なるご迷惑をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。
自由が丘南口改札口より徒歩1分の新築ビルですので、ご通院にはさほど支障はないと思っております。ビルの4階には2店舗ありまして、右側が美容室、左側が当院となります。なお、電話番号が変更しておりますのでご注意下さい。

今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
謹啓
晩夏の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より、皆様方のご支援ご厚情を賜り、深く御礼申し上げます。
さて、この度「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」に伴い、現在のクリニックの診療は本年9月21日(水)に診療を終了いたします。
移転先は自由が丘駅最寄りの現在建設中のビルで、本年12月に竣工予定でございます。
内装・移設工事などの関係で、診療再開は令和5年2月頃からを予定しております。詳細につきましては、今後あらためてお知らせいたします。
そのため、HPからの初診予約受付は再開まで一時停止させていただきます。治療内容によりましてはできる限り初診の方の対応もさせていただき
ますので先ずはお電話にてお問合せ下さい。(基本的には再診の方を対象に9月21日(水)まで対応させていただきます)。
再開までの期間、皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
まずは、書中をもちまして移転をお知らせいたします。 謹白
令和4年8月吉日 髙木歯科自由が丘クリニック
おかげさまで、当院は、令和4年1月11日をを持ちまして、開院10周年を迎える
ことになりました。
これもひとえに、当院を支援してくださった地域の方々、遠方よりわざわざ通院して
いただいている方々、ご指導をいただいた方々、日々ご紹介してくださる医療機関の先生方、
多くの方々に温かいご支援をいただいた賜物と心より感謝しております。
今後とも、皆さまの温かいご支援、ご指導を何卒よろしくお願い申し上げます。
令和4年1月11日、院長 髙木謙一
院長の髙木です。先日「口腔ケアの重要性」について日刊ゲンダイさんの取材を受けました。オーラルフレイル、アルツハイマー型認知症、誤嚥性肺炎について書かれています。現在とても重要視されている「口腔ケア」。お読みいただければ幸甚に存じます。
『驚愕!ずぼらな“口腔ケア”がアナタの人生を残酷に変える・・・!』という記事で紹介されています。
記事はこちらから
↓
https://kokuhaku.love/articles/10212
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当クリニックでは現在以下の対策を行っております。
①待合室に消毒液を設置しておりますのでご来院の際には手指の消毒をお願いしております。

こちらの消毒液は次亜塩素酸イオンをアルカリ水液中に安定化(仮眠状態のようなもの)させることに成功。
その結果、揮発することなく従来の次亜塩素酸系とまったく異なる性質が出現しました。
ph値は8.5~12.5の弱アルカリ性です。
細菌・ウイルス・バクテリアなど有機物(タンパク質)に接触すると遊離した次亜塩素イオンが直ちに反応し、それらを分解・消滅させることで除菌と消臭が瞬時に行われます。
除菌剤特有の刺激臭はなく無臭ですが(従来の次亜塩素酸ナトリウムは強烈な刺激臭)、細菌やウイルスなどの有機物に反応することで、塩素臭がします。しかし、反応後に残るのは酸素・水・微量の塩のみですので人にも環境にも安全・無公害です。従来の弱酸素性次亜塩素系は性質上、人の細胞を透過してしまうので本当に安全なものとは言えません。こちらの消毒剤は性質上、人の細胞を透過できないので、人にも肌にも安心して使用できて「除菌・消臭」効果が高い優れものです。コロナウイルスにも有効であるとのデータも出ております。
※アルコールではノロウイルスには効果がありません。アルコールの最大殺菌濃度が76.9~81.4であるため50%以下85%以上の濃度では他のウイルスに対しても殺菌力はほとんどありません。
②受付に飛沫防止のアクリルパーテーションを設置しました。

③診療時間中は窓や入口のドアを開け常時換気を十分に行い飛沫感染のリスクの低減を行っております。


④治療前に検温していただき37.5度以上の発熱がある場合は当日の治療は控えていただきます。
⑤治療器具は患者様ごとに交換し、消毒、高圧蒸気滅菌を行います(通常時でも行っております)。


⑥エプロン・紙コップはディスポーザブルのものを使用しております(通常時でも行っております)。

⑦術者は患者様ごとにグローブを交換して診療し、マスクを着用しております(通常時でも行っております)。また、必要によりゴーグルを着用します。
⑧治療前にうがいをしていただきます。

⑨ユニットやソファの消毒液による清拭を徹底しております(通常時でも行っております)。


⑩診療後のスピットンやバキュームの消毒液による除菌を毎回行っております(通常時でも行っております)。


⑪待合室の雑誌類を全て撤去いたしました。
⑫口腔内からの飛沫を抑制するため、緊急性のない治療は極力控え、応急処置に留めております。インプラント手術など緊急性のない治療は当面の間延期させていただきます。
海外から帰国後間もない方、37.5度以上の発熱のある方、味覚・臭覚に異常のある方、咳が長引いている方は大変恐縮ではございますがご来院をお控えいただけますようよろしくお願い申し上げます。
1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を心から願っております。
院長の髙木です。
本日、広尾の日赤医療センターの医師からのメッセージを頂戴しましたので是非とも拡散したいと思います。
「この数日でコロナウイルス感染症の患者さんが急増しています。
私の病院のコロナ病床は満床になりました。
重症者もいます。
現場ではすでに医療崩壊のシナリオも想定され始めています。」
「正直、報道よりも一般のみなさんが思っているよりも、現実は非常に厳しいです。
近い将来、本来助けられるはずの命が助けられなくなる事態になりそうだと感じています。
今まで、どんな人でも少しでも生きたいという思いがあるのなら、全力で命を助ける医療をやってきました。
でも、このまま感染が拡大すれば、「助ける命を選択する医療」にシフトしなければならなくなります。
本当に悲しい。」
「だから、外出を控えてください、人と会わないでください。
感染を食い止める方法はこれしかありません。
生きていくための最低限の外出だけにしてください。
このメッセージを出来る限りの家族や友人にシェアしてください。」
「時間がもうありません。
よろしくお願いします。」
続いては慶應義塾大学先端生命科学研究所、遺伝子制御の佐谷秀行先生からの情報です。
慶應でも院内感染が起こり、患者さんと知らぬうちに接触した医師や看護師にもPCR陽性者が出たようです。また、ほとんどの感染患者さんは食事中に感染しているようです。
佐谷先生がご自身でまとめられた感染防御マニュアルをイントラネットで公開されました。
以下 注意事項
↓↓↓
「ウイルスが出てくるのは咳とか唾とか呼気。 でも普通の呼気ではうつりません。 これまでのほとんどの感染は、①感染者から咳やクシャミで散った飛沫を直接吸い込む、②飛沫が目に入る、③手指についたウイルスを食事と一緒に嚥下してしまう という3つの経路で起こっています。
感染にはウイルス粒子数として100万個ほど必要です。一回のくしゃみや咳や大声の会話で約200万個が飛び散ると考えられています。つまり感染者がマスクをしているとかなり防ぐことができます。
なるべく鼻で息を吸いましょう。口呼吸で思い切りウイルスを肺の奥に吸い込むのはダメです。
外出中は手で目を触らない、鼻を手でさわらない(鼻くそをほじるのはNG)、唇触るのもだめ、口に入れるのは論外。 意外と難しいが、気にしていれば大丈夫です。
人と集まって話をする時は、マスク着用。 食事は対面で食べない、話さない。食事に集中しましょう。会話は食事後にマスクして。
家に帰ったら、速攻手を洗う。アルコールあるなら、玄関ですぐに吹きかけて、ドアノブを拭きましょう。
咽頭からウイルスがなくなっても、便からはかなり長期間ウイルスが排出されるという報告があります。ノロウイルスの防御法と同じように対処を忘れずに。
感染防御のルールを再度整理します。
①マスクと眼鏡の着用
②手指の洗浄と消毒
③会食は対面ではせず、一人で食事を短時間で済ませる
④外から帰宅時は先にシャワーを浴びてから食事
陽性患者さんの多くは、手指から口に入るか、食事の時に飛沫感染しているようです。
以上を守って元気でいましょう。」
皆様とこのような情報を共有したく公開しました。是非シェアして下さい。
くれぐれもお体ご自愛くださいますようお願い申し上げます。
院長の髙木です。
公益社団法人東京都玉川歯科医師会より以下の院内掲示の依頼がありました。
「誰かに移してしまう」可能性を認識して行動を!
今や、皆がコロナの保菌者である可能性があります。
1.37.5度以上の発熱の際は受診をお控えいただき、ご連絡下さい。
2.外出は必要最小限に控えて下さい。
3.夜間の外出は控えて下さい。
4.ご家族以外との会食はお控え下さい。
皆様一人一人の行動が今後の世の中を左右します。
★区民の皆様への緊急のお知らせ★
4月6日時点で、世田谷区において新型コロナウイルス感染者が143名に達しました。
間もなく「医療崩壊」が始まり、既に「非常事態」に陥っております。
院長の髙木です。
早くも新年会シーズンの到来ですね。
さて、私が所属しております、公益社団法人 東京都玉川歯科医師会におきましても去る1月9日(木)に二子玉川エクセルホテル東急30F「たまがわ」にて新年会が盛大に行われました。
18:30~開宴ですが、わたしは執行部(役員)としての準備がありましたので17:00には宴会場に到着しました。

開会の辞(島貫副会長)

大島会長よりご挨拶

乾杯のご発声(冨塚前会長)

2名の先生の古希のお祝いがおこなわれました。おめでとうございました!


歓談中の風景


各種委員会報告も行われました。

登録歯科衛生士の方々の挨拶

本会会誌の表紙写真コンテストの発表

閉会の辞(大倉副会長)

大変すばらしい1年の幕開けとなりました。
役員の先生方、ならびに福祉共済・厚生文化委員会の先生方大変お疲れ様でございました。